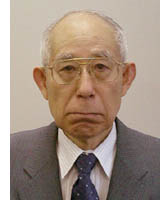|
|
|
●ご挨拶 |
|
|
|
●証明取得技術の紹介 |
|
|
|
●助成金の案内 |
|
|
|
●摩擦試験の紹介 |
|
|
|
●バージョンアップの紹介 |
|
|
|
●刊行物の紹介 |
|
|
|
●刊行物の紹介 |
|
|
|
●刊行物の紹介 |
|
|
|
●刊行物の紹介 |
|
|
|
●設計計算プログラムの紹介 |
|
|
|
●土木研究センター刊行物一覧 |
|
|
|
●複製刊行物一覧 |
|
|
|
●設計計算プログラムの一覧 |
|
|
|
●土木技術資料12月号目次 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり新年のご挨拶を申し上げます。 平成18年 元旦 |
|||||
|
|
|
建設技術審査証明取得技術の概要 |
|
|
|
新たに建設技術審査証明を取得した技術の概要を紹介します。 |
|
|
|
○ 先端翼付き回転貫入鋼管杭「ジオウィング・パイル」 |
||
|
依頼者 |
: |
住友金属工業株式会社 |
|
技術の概要 |
: |
「ジオウィング・パイル」は、鋼管杭の先端近傍に円周方向に3分割した先端翼を取り付け、地盤中に回転貫入することにより、無排土、低振動・低騒音での施工が可能である。先端翼は杭径の1.5倍または2.0倍の外径を有し、施工時は回転貫入のための推進力を発揮する。また、構造物からの荷重を地盤に伝達し、先端翼の径を直径とする支持面積によって従来の同径の打込み杭に比べて大きな先端支持力を得る役割を果たす。さらに、施工時の回転トルクと単位長さあたりの貫入時間などの計測データを用いて、リアルタイムで杭の貫入状況や支持層への到達を確認できる鋼管杭である。(広告の頁参照) |
|
審査項目 |
: |
(1) 環境への影響 (2) 杭の支持力 (3) 杭先端部の設計 (4) 施工管理 |
|
証明書 |
: |
「建技審証第0503 号」平成17年9月15日付 |
|
連絡先 |
: |
住友金属工業株式会社 建設技術部 |
|
|
||
|
建設技術審査証明事業についてのお問合せ先 |
|
|
|
財団法人土木研究センター 企画・審査部 田中 秀和 |
|
|
|
|
平成18年度「土木工学国際研究交流助成制度」について |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当センターでは、「土木工学国際研究交流助成制度」を実施しております。希望される方は、下記の応募要領に従い申請して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
当センターでは、11月1日より鉄線籠型護岸の蓋網部に使用される線材の面的摩擦試験を実施し、その材料の摩擦係数の試験成績書を発行しております。 |
|
|
|
|
|
1. 面的摩擦試験の概要 |
|
|---|---|
|
|
鉄線籠型護岸の蓋網部に使用される線材については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案)」(国土交通省河川局治水課)において、品質管理の手法としてメッキ工場における品質管理試験に加え、公的機関による試験を行い管理するよう規定されている。このうち摩擦抵抗については面的摩擦試験により摩擦係数を確認することとなっており、当センターにおける面的摩擦試験はこれに値するものである。 |
|
2. 実施要領 |
|
|
|
当ホームページの試験・検定を参照ください |
|
3. 試験費用 |
|
|
|
1試験片あたり21万円(税込み、報告書30部作成費用を含みます) |
|
4. 試験依頼資料 |
|
|
|
1) 面的摩擦試験依頼書 |
|
|
2) 試験片(幅1m×長さ1m) |
|
5. 申し込み先 |
|
|
|
財団法人 土木研究センター 研究開発三部 |
|
|
|
|
ジオテキスタイル緩勾配補強盛土設計システム(GEO-E2005) |
|
|
||||||
|
この度,GEO-E2002(ジオテキスタイル緩勾配補強盛土設計システム)をバージョンアップし,GEO-E2005を作成しました。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建設工事から発生する土砂を有効に利用するには、国土交通省では平成16年3月31日に通達:「発生土利用基準について」を関係機関に発出しました。ここでは、平成6年7月に建設省(当時)から発出された通達「発生土利用基準(案)について」の内容見直しが図られたほか、旧運輸省関係の工事にも対象を拡大、新たに都道府県及び政令指定市にも参考送付され、より一層の普及が図られることになっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目 次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
実務者のための養浜マニュアル |
|
|
||||||
|
22000年に施行された新海岸法では、砂浜が海岸保全施設として位置付けられた。しかしながら、これまでの海岸保全が主として海岸構造物を造ることを中心に行われてきたこともあり、従来の基準書等には、砂浜づくりについての技術的な知見が乏しいのが現状であった。 |
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
|
|
土木コンクリート構造物のはく落防止用 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
近年、構造物の維持管理技術の向上に対する関心は、行政および民間を含めて非常に高まってきています。特にコンクリート構造物においてはコンクリート表面のはく離・はく落の防止は維持管理上重要な技術の一つであり、その原因となるコンクリ-トの変状を容易にかつ経済的に調査する技術の開発発展が求められています。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||

|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
グラウンドアンカー受圧板 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
新潟県中越地震の被害例でも明らかなように、災害の防除のために、安定性を強化しなければならない傾斜地や地すべり地域がわが国にはまだ沢山あります。グラウンドアンカーによる補強対策は優れた対策工法のひとつで、そのための必要なアンカーの設計施工の基準類も完備しています。しかしながら、アンカーの荷重を地表で受ける受圧板の設計法については、多くの受圧板が使用されている割には統一された基準がなく、その確立が待たれています。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
各種の設計システム |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
実務者のための養浜マニュアル |
|
|
|
|
|
|
|
土木コンクリート構造物のはく落防止用赤外線サーモグラフィによる変状状調査マニュアル |
|
|
|
|
|
|
|
グラウンドアンカー受圧板設計・試験マニュアル |
|
|
|
|
|
|
|
建設発生土利用技術マニュアル 第3版 |
|
|
|
|
|
|
|
陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル改訂版 |
|
|
|
|
|
|
|
補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル 第3回改訂版 |
|
|
|
|
|
|
|
護岸ブロックの水理特性試験法マニュアル第2版 |
|
|
|
|
|
|
|
多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第3版 |
|
|
|
|
|
|
|
炭素繊維シートによる鋼製橋脚の補強工法ガイドライン(案) |
|
|
|
|
|
|
|
ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装の設計・施工マニュアル-路床/路盤分離材としての利用- |
|
|
|
|
|
|
|
超早強コンクリート利用技術マニュアル |
|
|
|
|
|
|
|
ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル改訂版 |
|
|
|
|
|
|
|
平成9・10年度耐震設計ソフトウェアに関する研究委員会報告書 |
|
|
|
|
|
|
|
炭素繊維を用いた耐震補強法研究会平成8・9年度報告書 |
|
|
|
|
|
|
|
発生土利用促進のための改良工法マニュアル |
|
|
|
|
|
|
|
平成8年度耐震設計ソフトウェアに関する研究委員会報告書 |
|
|
|
|
|
|
|
風土工学の誕生 |
|
|
|
|
|
|
|
テクソル・グリーン工法―高次団粒基材吹付工―設計・施工マニュアル |
|
|
|
|
|
|
|
斜張橋ケーブルの耐風性検討 報告書 |
|
|
|
|
|
|
|
斜張橋ケーブルの耐風性検討 資料編編 |
|
|||||
|
コンクリ-トの耐久性向上技術の開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構造物の防汚技術の開発 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
第5次土木研究所研究五カ年計画 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
斜張橋並列ケーブルのウェークギャロッピング制振対策検討マニュアル(案) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
熱赤外線映像法による吹付のり面老朽化診断マニュアル |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
九州地建における1日土研資料 平成6年度 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
建設省 道路橋の免震設計法マニュアル(案) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
道路橋の耐震設計法 (ビデオ版) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
橋の耐震設計技術 (ビデオ版) 英語版有 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
自動運転道路システム・概要編 (ビデオ版)英語版有 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
自動運転道路システム・技術記録編 (ビデオ版)英語版有 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
建設省土木研究所における高度道路交通システムへの取り組み(ビデオ版) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
多自然型川づくり (ビデオ版) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年度国土交通省国土技術研究会報告 |
国土交通省 |
|
|
|
|
|
|
|
第51回~54回建設省技術研究会報告 |
建設省 |
|
|
|
|
|
|
|
第49回建設省技術研究会報告 |
建設省 |
|
|
|
|
|
|
|
第44回~45回 建設省技術研究会報告 |
建設省 |
|
|
|
|
|
|
|
第43回 建設省技術研究会報告 |
建設省 |
|
|
|
|
|
|
|
第37回~42回 建設省技術研究会報告 |
建設省 |
|
|
|
|
|
|
|
第35回~36回 建設省技術研究会報告 |
建設省 |
|
|
|
|
|
|
|
UJNR 第25回~28回合同部会概要(日本語版) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
UJNR 第27回合同部会会議録(英語版) |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
UJNR 第25回合同部会概要 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
UJNR 第23回~25回合同部会会議録 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
UJNR 第21回合同部会会議録 |
建設省土木研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ジオテキスタイル盛土排水・補強盛土設計システム |
GEO-D2002 |
ジオテキスタイル補強土工法普及委員会 |
|
|
|
|
|
ジオテキスタイル緩勾配補強盛土設計システム |
GEO-E2005 |
ジオテキスタイル補強土工法普及委員会 |
|
|
|
|
|
ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム |
GEO-W2002 |
ジオテキスタイル補強土工法普及委員会 |
|
|
|
|
|
補強土(テールアルメ)壁工法設計システム |
GEO-RE2004 |
システム開発研究会 |
|
|
|
|
|
多数アンカー式補強土壁工法設計システム |
GEO-MA2004 |
システム開発研究会 |
|
|
|
|
|
擁壁の支持力計算プログラム |
GEO-BC2004 |
システム開発研究会 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
(特集:自然と共生する国土の再構築に向けて) |
|
区分 |
題名 |
著者名 |
頁 |
|---|---|---|---|
|
表紙 |
自然と共生する国土の再構築に向けて |
福田晴耕 |
|
|
グラビア |
「自然共生型流域圏・都市の再生」~実践に向けた政策検討ツールの開発~ |
小路剛志、長濵庸介 |
|
|
巻頭言 |
年頭の挨拶 “経済”を超えて |
望月常好 |
|
|
巻頭言 |
年頭の挨拶 |
坂本忠彦 |
|
|
速報 |
平成17年9月台風14号豪雨による宮崎県地すべり災害速報 |
藤澤和範、神原規也 |
|
|
ニュース |
「計測・制御・自動化に関する国際会議(ICA2005)」参加報告 |
小森行也 |
|
|
ニュース |
第16回国際地盤工学会議に参加して |
長屋和宏、高山丈司 |
|
|
研究コラム |
水圧破砕に着目したロックフィルダムのコア幅設計に関する研究 |
山口嘉一、冨田尚樹 |
|
|
研究コラム |
地震時の被害把握におけるCCTVカメラの効果的活用手法 |
真田晃宏 |
|
|
土木技術講座 |
道路橋の損傷と対策(第3回)~道路橋コンクリート部材の損傷事例とその対策~ |
渡辺博志 |
|
|
土木技術講座 |
ダム貯水池の有効活用技術(第4回)~貯水池の堆砂排除技術~ |
柏井条介 |
|
|
論説・企画趣旨 |
|
||
|
報文(特集) |
|
||
|
報文(特集) |
|
||
|
報文(特集) |
|
||
|
報文(特集) |
|
||
|
報文(特集) |
|
||
|
報文(特集) |
|
||
|
報文 |
|
||
|
報文 |
|
||
|
報文 |
|
||
|
編集後記 |
|
白土真大 |
|
|
|
|